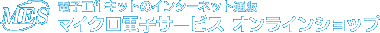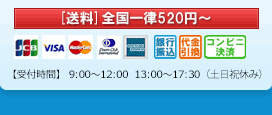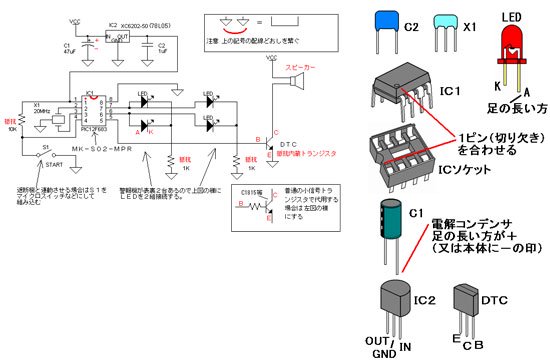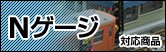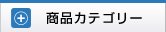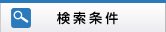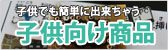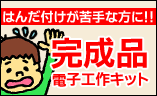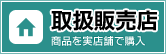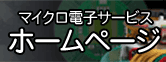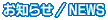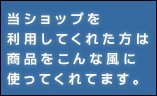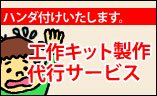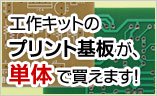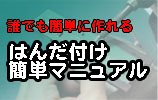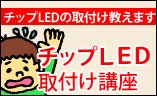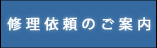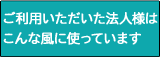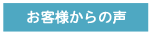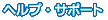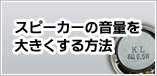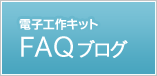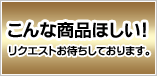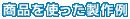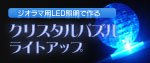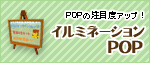�ץ�졼���HO����������٤ơ�N�������ؤα��Ѥ�����٤��⤤�Ǥ��������������������ܼ�ξ��·�äƤ��ơ��Ϸ�����¿��N�������������ä��ߤ������åȤǤ��Τǡ������Ҳ𤷤ޤ�������Ϸ��ΤߤǼ��ǵ�����ޤ���Τǡ�����3��Ƨ�ڡפˤʤ�ޤ���
| ��1��TOMYTEC �������쥷��� ��ʾ�ʪ001 ��Ƨ�ڡ� |
��2��Ŵƻ�Ϸ���LEDƧ�ڲ� ���ʥ��åȡ�N�������ѡ� |
��3�ˤ���¾ |
|---|---|---|
 |
 ���å�LED��1608��������/��1K����10K����/�Ų�ǥ�22��F��47��F 16V��/����ߥå�����ǥ�0.1��F��/����ߥå�ȯ���ҡ�20MHz��/IC�����åȡ�8Pin��/����¢�ȥ������DTC114��/��ü�ҥ쥮��졼������78L05��/���ѥץ��ȴ���/���ԡ�������8����32����/������ |
|
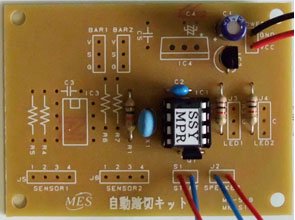 ��1.���ѥץ��ȴ��Ĥ����ʤ������
��1.���ѥץ��ȴ��Ĥ����ʤ������
�����˽��������ѥץ��ȴ��Ĥ����ʤ�Ϥ���դ����ޤ���
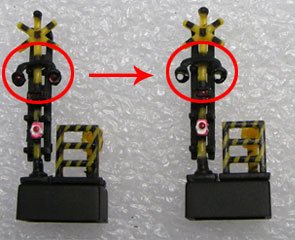 ��2.���Υ�����ʬ�ηꤢ����
��2.���Υ�����ʬ�ηꤢ����
�ڥ�ʤɤǰ����դ����������ַ��Ť˹Ԥ��ޤ������Υ�����ʬ��1���η���ޤ���
���פ�¦��٤��ˤʤ�褦��ʪ������Ƥ����ȡ��ץ饹���å��˳ݤ�����ô���ڸ����졢�ޤ���ɤ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
������塢�ֿ����������Ĥä��ޤޤξ��ϡ����������⤷���ϥڥ���ȥޡ��������ɤäƤ����ޤ���
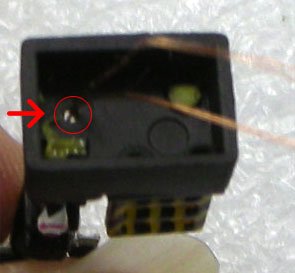 ��3.���Υ١�����ʬ�ηꤢ����
��3.���Υ١�����ʬ�ηꤢ����
�١�����ʬ�ˤ������Ѥη��1���dz����ޤ���
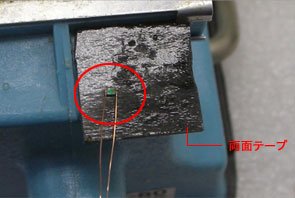 ��4.���å�LED�ˤϤ���դ���
��4.���å�LED�ˤϤ���դ���
���å�LED�������ѤΥ��ʥ������ϥ���դ����ޤ���
���å�LED��̿��Τ褦��ξ�̥ơ��פ�Ž���դ��Ƹ��ꤷ�Ƥ����ȡ�LED��������ꤻ���˰��ꤷ�ƥϥ����Ȥ�Ԥ����Ȥ�����ޤ���
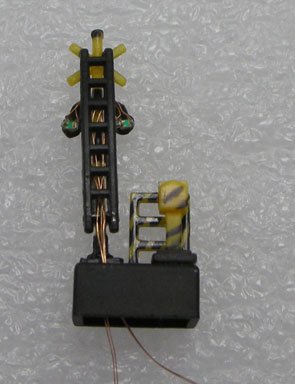 ��5.LED������Ȥ߹����
��5.LED������Ȥ߹����
���å�LED�����¦����ִ�����ޤ�Ž���դ��ޤ��������ϥϥ�������������̤�����Ω���ʤ����ޤ��礦��
������¦���鸫���Ƥ��륨�ʥ�����ȥ��å�LED�����������ڥ���ȥޡ��������ɤ���ɤ��Ǥ��礦��
�١����η���̤��ȡ��̿��Τ褦�ˤʤ�ޤ���
����ޤ��������顢¦����������DZ����ޤ�����LED�θ�ϳ���к��ˤϡ������ɤ�Ťͤ�ɬ�פ�����ޤ���
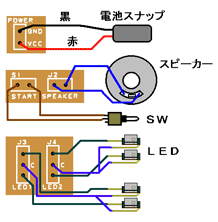 ��6.�ƥѡ��Ĥ�������
��6.�ƥѡ��Ĥ�������
���������ޤ˽��������ѥץ��ȴ��Ĥȡ������å������ӥ��ʥåס����ԡ�������LED���դ�������Ҥ��Dz�������
��7.������
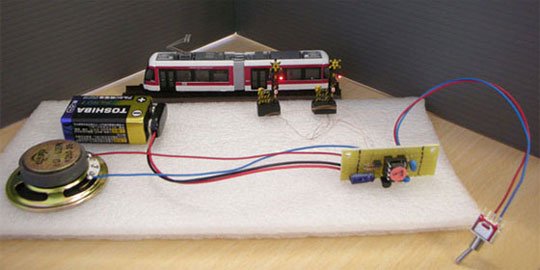
���åȤ���³����LED�����������Ƥ����ͻҡ��ʥ������İ��ΰ١���ξ���֤��Ƥ��ޤ��� | |
 �쥤�����Ȥ��Ȥ߹���Ǵ����Ǥ��� |
 N��������Ƨ���ڤ�⤳���ޤǼ´�Ū�ˤʤ�ޤ��� |

|
N������Ƨ�ڥ��å� ��¸��Ƨ���Ϸ��˼���դ��뤳�Ȥǡ��ٹ�����������Ƨ�ڲ����Ĥ餹���Ȥ��Ǥ���褦�ˤʤ�ޤ��ʥ����å�����ˡ�N�������˺�Ŭ���礭���Υ��å�LED��1608������/1005�������ˤȥݥꥦ�쥿�����Υ��åȡ� |

|
�Υ�������ưƧ�ڥ��å� Ƨ�ڥ��åȤ��Ϸ���ξ���̲�˹�碌�Ƽ�ư����Ǥ���褦�ˤ������åȤǤ���N�������˺�Ŭ���礭���Υ��å�LED��1608������/1005�������ˤȥݥꥦ�쥿�����Υ��åȡ� |

|
�ڴ����ʡ� N������Ƨ�ڥ��å� �Ϥ���դ������Ѥߤ�N��������Ƨ�ڥ��åȴ����ʤǤ��� |